7.苦悩の始まりジャコビニ群の夜
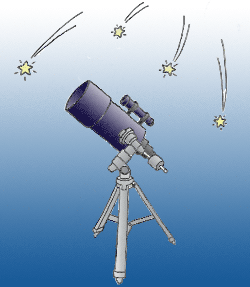
1998年は,13年に一度訪れるジャコビニ流星群の極大の年に当たっていた。
大騒ぎされた上に不発だった26年前と,ハレー騒ぎに霞んでしまった13年前。大方の人々と同じように両者とも見逃してしまった私にとって,いくら流星観測一般にあまり興味がなかろうと,この流星群の極大だけは特別だった。ふわっと尾を引いて流れるという噂のジャコビニ群の群流星を,是非とも一度は見てみなければ。
満月を過ぎたばかりの大きな月に照らされながら,10月8日の夜,亮介と私は翌日を有給休暇にして体制を整え,出現するかどうかもよく分からないジャコビニ群を待ちに出かけた。
仕事を終えて一旦帰宅した後の出発なので,観測地への到着は必然的に遅くなる。私たちは何度も何度も空を仰ぎ,極大が今でないことを祈りつつ車をとばした。やっと観測地にたどり着いたのは22時前。
早速寝転んで空を見上げると,憧れのジャコビニ群は,私たちの到着を待っていたかの如くバシバシ流れ始めた。何と運が良かったことだろう! そして,30分ほどのピークを終えると一気に流れなくなった。空は快晴。
だが,どう見てもすでにピークを終えてしまって流れそうにもない流星群をこれ以上待ち続けても仕方がない。木星を見てもシーイングが悪い。かといって,立待月が燦々と輝く中で,星座を楽しむこともままならぬ。
快晴の夜空の下で,見るものに困り持て余していると,亮介が言った。
「ミラを観よう。」当然予想できる展開だった。けれど,私は戸惑った。
月明かりのため肉眼で3等星を認めることでさえ厳しい状況だというのに,あの,あの暗いミラを導入するというのか。
勿論,月明かりがあったとしても,望遠鏡に導入できさえすればミラを観測することは可能だろう。それくらいのことは知っていたが,この空の下で導入するということそのものが,私には現実離れした行為に思われた。
だが,戸惑っている私をよそに,すでに亮介は星図を見ながら双眼鏡でミラの位置を確認し始めていた。空は明るく,しかもファインダーは慣れない倒立だ。さすがの亮介も,この夜の導入には苦労しているようだった。しばらく待っても,なかなか入ったという声がかからない。話しかけてみても,星探しに懸命な彼の耳には届かないようで返事がない。亮介は,ミラを見つけることに本当に一生懸命になっていた。その姿は衝撃だった。
私には,とてもここまで熱心に,目標の星を探す気力はないだろう。ミラのような暗い星は,この悪条件の中でさえ,こんなにも一生懸命になれる人が観測すべき星なのではないか。私のように,導入する気にもなれない者が観測して,何になるというのだろう。私には,観測する資格がない。
もちろん,趣味で星を見るアマチュアに観測資格なんてものがある筈もない。
だが,それは私の美学だった。いろんな過去が,脳裏に甦る。
私は確かに怠惰な観測ミーハーかもしれないけれど,観測するというからには,自分で自分の面倒を見てきたつもりだ。わからないながらも自分で観測機材を調達したし,重くたって自分で機材を運び組み立てた。観測準備は自分で行う。そんなことは,考えるまでもなく当然のことだった。
それなのに,今,私は亮介に設定してもらった環境をそのまま享受して,目測だけをやろうというのか? 自分でミラを導入できるが今日はたまたま彼が導入している,というのなら,それもよかろう。しかし違った。私はミラがどこにあるのだかもわからないのだ。一体全体どの面下げて,どこにあるのかも知らない星を「観測しました」なんて言えるだろうか。とてもじゃないが,言えやしない。観望(見るだけ)ならいい。でも観測(観ること)はダメだ。絶対に。
誰もそんなことを気にとめないだろうし,責めもしないだろう。だけど,私自身がそれを許せないのだった。単純に,ミラを観たいという気持ちはあった。それに亮介は,私にも観てもらおうとして導入しているに違いなかった。もし私が観ないと言ったら,彼はさぞかしがっかりすることだろう。
それでも自分で導入できないままにミラを観ることは,今までの自分の姿勢を裏切ることだった。あぁ,それに,私は知っていた。観測の楽しみは,対象天体を導入しようとしたその瞬間から始まるのだということを。たくさん迷って考えたけれど,その夜の私にできたのは,唯一,ミラを観ないという選択だけだった。